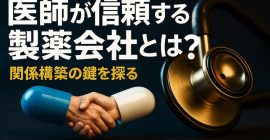皆さんは「建設業界」と聞いて、どのようなイメージを抱くだろうか。
おそらく、多くの人が「きつい」「汚い」「危険」といった、いわゆる3Kのイメージを連想するのではないか。
確かに、かつての建設現場はそうした側面が強かったかもしれない。
しかし、近年では労働環境の改善や安全対策の強化、そしてICT技術の導入など、業界全体で大きな変革が進んでいる。
私は、岡本博之と申します。
早稲田大学理工学部を卒業後、大手ゼネコンで約25年間、高速道路やトンネルなどの建設プロジェクトに携わってきました。
40代で広報部門に異動し、現在はフリーの建設系ライターとして、業界の課題や魅力を発信する活動をしています。
本記事では、長年の現場経験と広報の知見を持つ私が、建設業界のイメージを変えるための「広報戦略」と「情報発信」の新たな試みについて、具体的な事例を交えながら解説していきたい。
建設業界が抱える課題を直視しつつ、その魅力をどう伝えれば良いのか。
一緒に考えていきましょう。
目次
建設業界のイメージ変革に向けた現状と課題
まず、建設業界の現状と課題を整理します。
ここでは、統計データや社会的認知の分析を通じて、業界が直面する問題を明らかにします。
業界の課題を示す統計データと社会的認知
厚生労働省の「労働安全衛生調査」によると、建設業の労働災害発生率は全産業平均と比べて依然として高い水準にある。
- 2022年の建設業における労働災害による死亡者数:288人
- 休業4日以上の死傷者数:14,932人
この数字は、建設現場が依然としてリスクを伴う職場であることを示している。
また、日本建設業連合会が実施したアンケート調査では、建設業に対する一般のイメージとして、次のような意見が多く挙げられた。
- 長時間労働が常態化している
- 休暇が取りにくい
- 肉体的にきつい仕事が多い
こうしたデータから、建設業界に対するネガティブなイメージが根強く存在することがわかる。
長時間労働・安全管理・人材不足がもたらす影響
建設業界の課題として、長時間労働、安全管理、人材不足が挙げられます。
これらの問題が業界のイメージにどのような影響を与えているのかを、詳しく見ていきましょう。
長時間労働は、労働者の健康を害するだけでなく、生産性の低下にもつながります。
安全管理の不備は、重大な労働災害を引き起こすリスクを高め、業界全体の信頼を損ないます。
そして、これらの要因が複合的に作用することで、建設業界は深刻な人材不足に陥っているのです。
国土交通省の調査によると、建設業の技能労働者は、2025年には約130万人不足すると予測されています。
これらの課題は、建設業界のイメージを悪化させる大きな要因となっている。
では、どうすればこの状況を改善できるのか。
ここで、ある企業の取り組みを例に挙げてみましょう。
大手ゼネコンのA社は、労働環境の改善に積極的に取り組んでいます。具体的には、ICT技術を活用した業務効率化や、週休2日制の導入などを進めています。その結果、社員の残業時間は大幅に削減され、有給休暇の取得率も向上しました。こうした取り組みが評価され、A社は「働きやすい企業ランキング」で上位にランクインするなど、企業イメージの向上に成功しています。
このように、現場の労働環境改善に真摯に取り組むことで、企業イメージ、ひいては業界全体のイメージを向上させることが可能となるのです。
以降のセクションでは、具体的な広報戦略と情報発信について、詳しく見ていきましょう。
新しい広報戦略の考え方
イメージを刷新するためには、従来の広報活動の枠を超えた、新たな戦略が求められます。
ここでは、ターゲットに応じたメッセージの最適化と、現場のリアルを伝えるコンテンツ作成のポイントを解説します。
ターゲットに応じたメッセージの最適化
広報活動において重要なのは、ターゲットを明確にし、それぞれに最適なメッセージを届けることです。
建設業界のステークホルダーは多岐にわたります。
| ターゲット層 | 関心事・ニーズ | 伝えるべきメッセージ |
|---|---|---|
| 若年層・学生 | キャリアパス、働きがい、技術革新 | 将来性、成長機会、社会貢献度 |
| 建設業従事者 | 労働環境、待遇、安全対策 | 働きやすさ、キャリアアップ、安全への取り組み |
| 発注者・行政機関 | 品質、コスト、工期、コンプライアンス | 技術力、信頼性、法令遵守、社会的責任 |
| 地域住民 | 工事の影響、安全性、環境への配慮 | 安全対策、騒音対策、環境保護活動 |
このように、ターゲットごとに異なる関心事やニーズが存在します。
それぞれの視点に立ち、最適なメッセージを発信することが重要です。
例えば、若年層や学生に対しては、建設業界の将来性や技術革新、社会貢献度の高さをアピールすることが効果的です。
一方、発注者や行政機関に対しては、品質やコスト、コンプライアンスに関する取り組みを強調することで、信頼を獲得できます。
また、建設業界のDXを推進するBRANU株式会社のように、デジタルツールを活用して業務効率化や情報共有の円滑化を図ることも、業界全体のイメージアップに繋がるでしょう。
同社は、建設事業者向けマッチングサイト「CAREECON」や、統合型ビジネスツール「CAREECON Plus」などを提供し、業界の生産性向上に貢献しています。
現場のリアルを伝えるコンテンツ作成のポイント
建設業界のイメージを変えるには、現場のリアルな姿を伝えることが不可欠です。
しかし、単に現場の様子を紹介するだけでは、十分な効果は得られません。
ここでは、現場のリアルを伝えるコンテンツ作成のポイントを、以下の3つの観点から解説します。
- ストーリーテリングの活用
- 現場で働く人々の声の紹介
- 専門用語のわかりやすい解説
まず、ストーリーテリングを活用することで、読者の共感を呼び起こすことができます。
例えば、一つのプロジェクトが完成するまでの過程を、携わった人々の思いと共に描くことで、仕事のやりがいや達成感を伝えることができます。
次に、現場で働く人々の声を紹介することも重要です。
実際の労働者の生の声は、何よりも説得力があります。
安全への取り組みや労働環境の改善について、現場の視点から語ることで、より多くの人々に届けることができます。
最後に、専門用語のわかりやすい解説も欠かせません。
建設業界には、一般の人には馴染みのない専門用語が多く存在します。
例えば、「スランプレシオ」という言葉をご存知でしょうか。
これは、コンクリートの流動性を示す指標で、数字が大きいほど柔らかいコンクリートを意味します。
このように、専門用語を噛み砕いて説明することで、幅広い読者層への理解を促進できます。
これらのポイントを押さえたコンテンツ作成により、建設業界のリアルな姿を伝え、イメージ向上につなげることができるでしょう。
情報発信の新たな試みと実践例
効果的な広報活動を展開するには、新しい情報発信の手法を取り入れることが重要です。
ここでは、SNSや動画を活用した効果的な発信手法、現場インタビューとライブ配信による信頼醸成、そしてインフラツーリズムによる地域活性化とイメージアップの融合について、具体的な実践例を交えて解説します。
SNSや動画を活用した効果的な発信手法
近年、情報発信の手段として、SNSや動画の重要性が増しています。
建設業界においても、これらのツールを活用した効果的な発信が求められています。
- X(旧Twitter):現場の進捗状況や安全への取り組みをリアルタイムで発信
- Instagram:迫力のある現場写真や動画を投稿し、視覚的に訴求
- YouTube:長尺の動画コンテンツで、プロジェクトの裏側や技術解説を配信
これらのSNSを効果的に使い分けることが重要です。
例えば、ある建設会社では、次のような取り組みを行っています。
- Xで毎日の安全確認の様子を「#今日の安全確認」というハッシュタグ付きで投稿
- Instagramで「#建設現場の美しい瞬間」という企画を実施し、一般から写真を募集
- YouTubeで、ベテラン技術者による若手への技術継承の様子をシリーズ動画で配信
これらの取り組みにより、この建設会社は、SNS上で多くのフォロワーを獲得し、業界内外から注目を集めることに成功しています。
特に、一般からの写真募集企画は、建設現場に対する親近感を醸成するのに効果的でした。
現場インタビューとライブ配信による信頼醸成
情報発信において、信頼性を高めることは非常に重要です。
そのための有効な手段の一つが、現場インタビューとライブ配信です。
現場インタビューでは、実際に現場で働く人々の生の声を聞くことができます。
例えば、以下のような質問を投げかけることで、リアルな現場の姿を伝えることができます。
- 現在、どのような業務を担当していますか?
- 仕事のやりがいや苦労はどのような点ですか?
- 安全管理のために、どのような取り組みを行っていますか?
これらの質問を通じて、現場で働く人々の率直な意見を引き出すことが重要です。
また、近年では、ライブ配信を活用した情報発信も注目を集めています。
例えば、ある建設会社では、以下のような取り組みを行っています。
毎週金曜日の17時から、現場監督によるライブ配信を実施。
工事の進捗状況や、安全管理のポイントなどをリアルタイムで解説。
視聴者からの質問にもその場で回答。この取り組みにより、この建設会社は、透明性の高い情報発信を実現し、ステークホルダーからの信頼を獲得することに成功しています。
特に、視聴者からの質問にその場で回答することで、双方向のコミュニケーションを実現し、より深い理解と信頼を得ることができました。
インフラツーリズム:地域活性化とイメージアップの融合
近年、インフラツーリズムという新たな観光形態が注目を集めています。
これは、ダムや橋梁、トンネルなどの巨大インフラを観光資源として活用するものです。
建設業界にとって、インフラツーリズムは地域活性化とイメージアップを同時に実現する可能性を秘めています。
例えば、黒部ダムでは、ダムの壮大さや建設の歴史を学べる観光放流が人気を集めています。
また、明石海峡大橋では、普段は立ち入ることができない主塔に登るツアーが実施されています。
これらの取り組みは、観光客に感動を与えるだけでなく、建設業界の技術力の高さをアピールする絶好の機会となっています。
さらに、インフラツーリズムは地域経済の活性化にも貢献します。
観光客の増加は、地元の宿泊施設や飲食店などの利用を促進し、地域経済に好循環をもたらします。
ここで、ある自治体の取り組みを紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象インフラ | 大規模ダム |
| ツアー内容 | ダム内部の見学、建設技術の解説、放流体験 |
| 参加者数 | 年間約1万人 |
| 経済効果 | 約5億円(観光消費額) |
| イメージ向上効果 | 参加者の90%以上が「建設業界のイメージが良くなった」と回答 |
この取り組みにより、この自治体は、観光客の誘致に成功しただけでなく、建設業界のイメージ向上にも大きく貢献しました。
インフラツーリズムは、建設業界の新たな可能性を切り開くものと言えるでしょう。
まとめ
本記事では、建設業界のイメージを変えるための広報戦略と情報発信の新たな試みについて、私の経験と知見を基に解説してきました。
建設業界は、労働環境や安全管理、人材不足など、多くの課題を抱えています。
しかし、同時に、社会に不可欠なインフラを支える、大きなやりがいと魅力のある業界でもあります。
その本質的な魅力と社会的意義を再評価し、広く伝えることが、今、求められています。
業界内外に向けた情報発信の重要性は、今後ますます高まっていくでしょう。
SNSや動画の活用、現場の声の紹介、インフラツーリズムなど、新たな発想と手法を取り入れることで、建設業界のイメージは大きく変わるはずです。
私自身、これからも建設系ライターとして、業界の発展に貢献していきたいと考えています。
読者の皆さんにも、ぜひ建設業界の「今」に注目し、その魅力を再発見していただきたいと思います。
そして、共に建設業界の明るい未来を築いていきましょう。
それが、本記事の最終的なメッセージです。